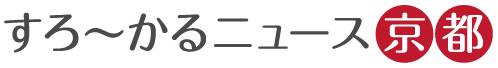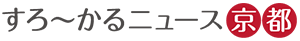京都の女の人の言葉が優しく聞える

大正から昭和にかけて、詩人・小説家として生きた室生犀星。代表作の一つ『小景異情』が、広く知られています。
小景異情―その二
ふるさとは遠きにありて思ふもの
そして悲しくうたふもの
よしや
うらぶれて異土の乞食かたゐとなるとても
帰るところにあるまじや
ひとり都のゆふぐれに
ふるさとおもひ涙ぐむ
そのこころもて
遠きみやこにかへらばや
遠きみやこにかへらばや
今回紹介する『京洛日記』は、室生犀星が1930年に京都旅行をした際の想い出を書いたもの。その一部を掲載します。
十八、旅愁
京都に寺院や庭を見に來る人は大抵二日くらゐで歸つてしまふが、殊に庭を見る人は一日に三つ以上の庭を見るのは無理である。一日に二つくらゐ見てをれば感じが紛れなくてよい。僕は三つくらゐ見て歩いたが手帳にでも書いておかないと、佳いところを見ても忘れてしまふやうになるのだ。
どこの寺でも庫裏の板の間や廊下、戸や障子といふものが煤光りがして美しかつた。こつくりした煤色の材木が何ともいへない古さを持つてゐる。それに濕氣のある土地だけに瓦に苔があつて、瓦の立派さとよく釣り合つて美しい。
太秦村に大河内傳次郎君をたづねると、四年前に逢つた時とは少し肥つて好い血色をしてゐた。僕は鼠小僧の解決篇を見ないので、今夜で、替るといふので町へ行つて二人で見物した。自分の主演映畫を見たらどんな氣がするか分らないが、大河内君は神妙にだまつて見物をしてゐて、濟むまで何もいはなかつた。僕もいはなかつた。
京都の市中の家々の庭などで小さいものでかなりによく出來たものもあるらしいが、さういふ町家の庭といふものを一つも見なかつた。却つて名苑などと違つた意味で、そんな庭に呼吸を吹きかけたいやうな好い庭があるかも知れない。朝はいつも曇つてゐて、日が射しても明るくないぼんやりした日ざしは薄ら寒く、どこの庭を見て歩いても苔が生えてゐて、日かげによく調和して沈んだ色に見えたのである。空氣や濕度、不快活な日光などがどれだけ、京都の庭をよく育てゝゐるかも知れないのだ。
京都の女の人は大てい言葉つきから或る親しみが感じられるが、實際は言葉の優しさが性格にあるかどうか分らない。たゞ、東京辯の鋭い調子ばかり聞いてゐる僕などは、ひつそりと入つて來て用事をして呉れる旅籠屋の女中が、時時に物をいふ言葉を聞いてゐると大變に柔和に、心持ちよく接せられるやうである。外ではそれほどではないが、旅籠屋の靜かな部屋のなかでは一入に京都の女の人の言葉が優しく聞える――殊に僕などのやうに滅多に旅行をしない人間に取つては、京の女はたとひ少し綺倆がわるくても旅愁くらゐは感じさせてくれるやうである。或ひは綺倆がわるいほど旅愁が旅愁らしく感じられるかも知れぬ。美人といふものは騷々しい感じがするものであるが、綺倆のわるい女ほど靜かで、質のよい女になると美人よりもつとシンミリした味ひをもつてゐるものである。
(『京洛日記』から一部抜粋)